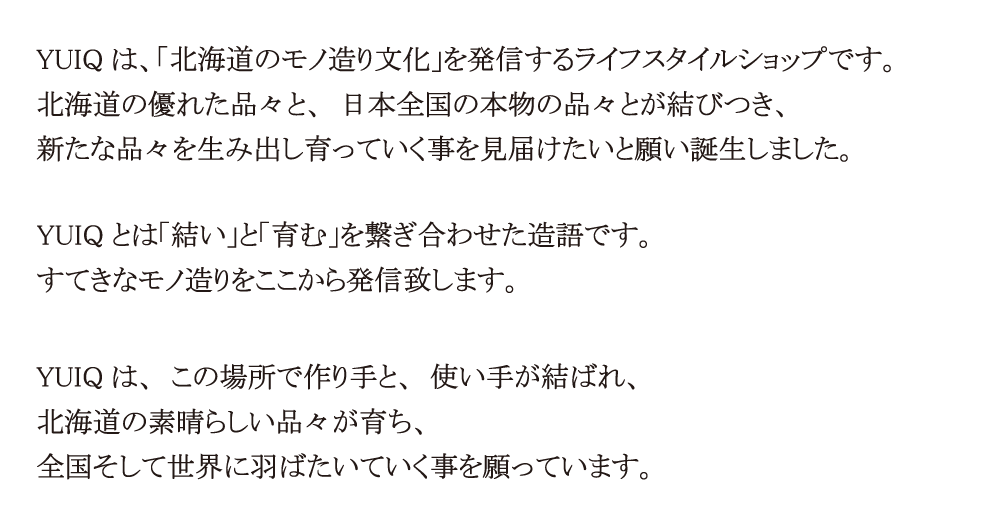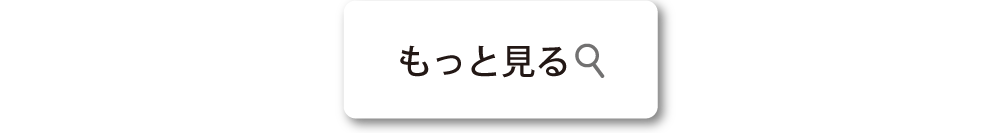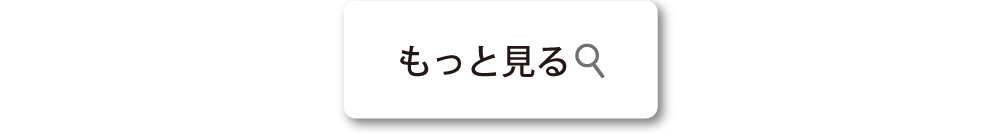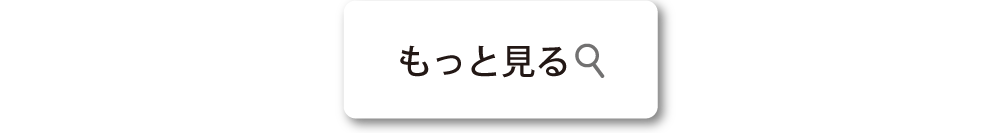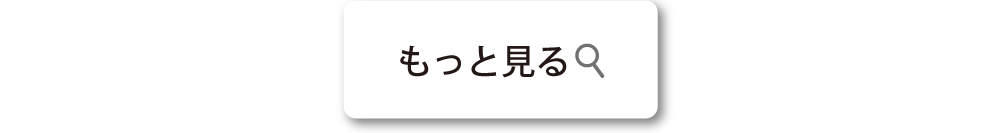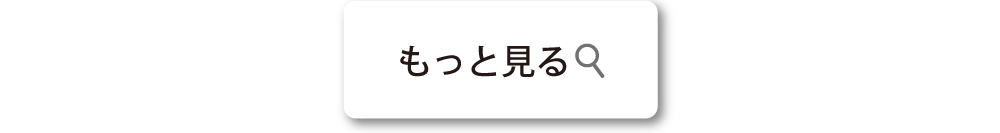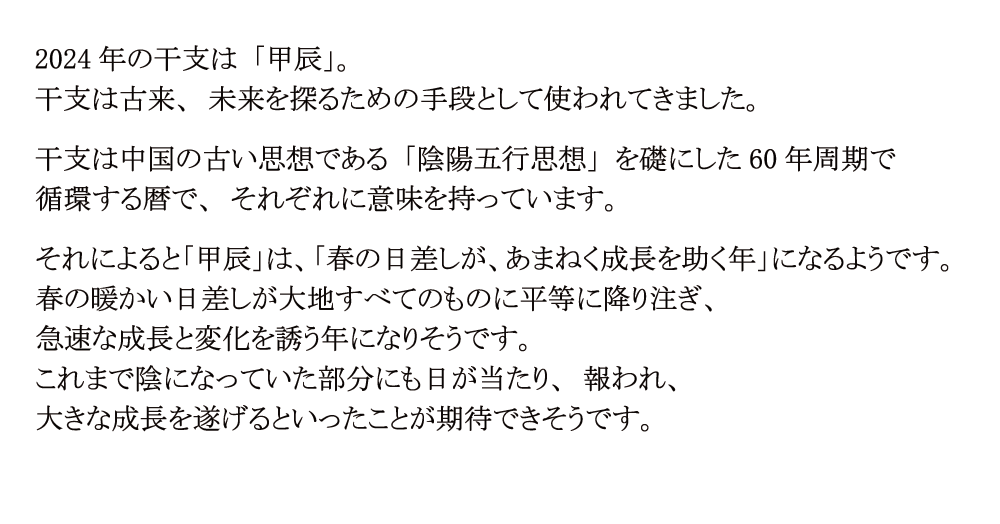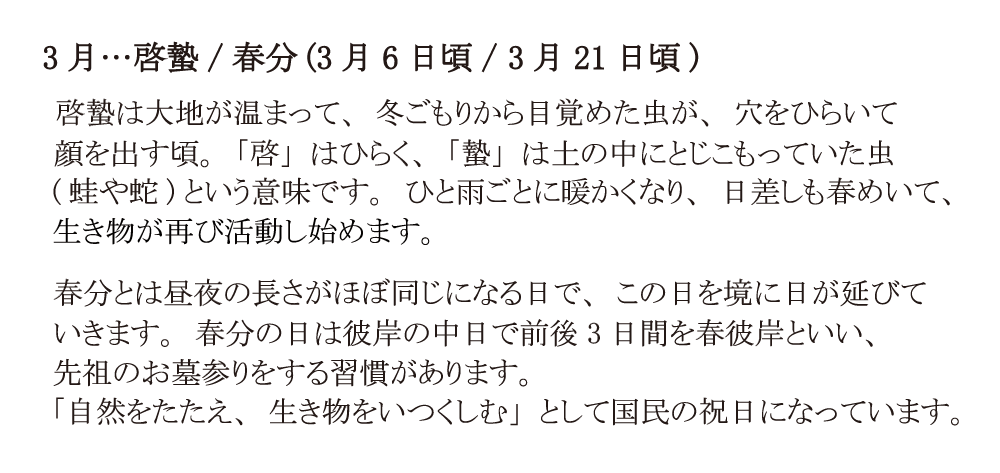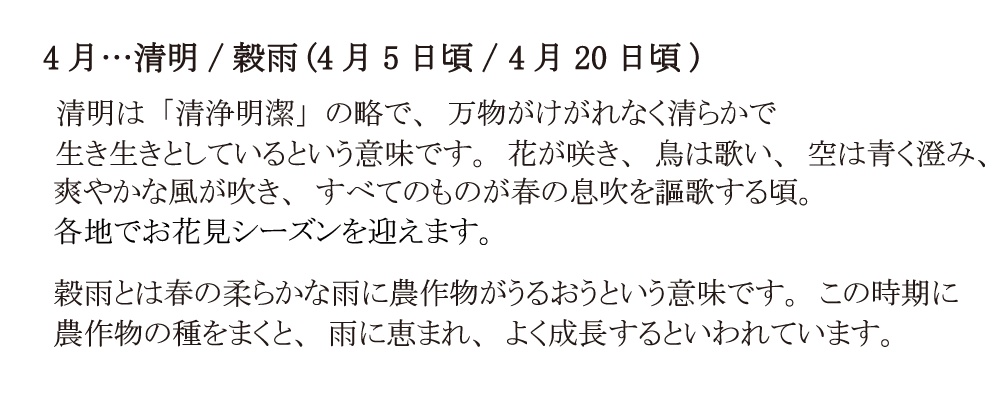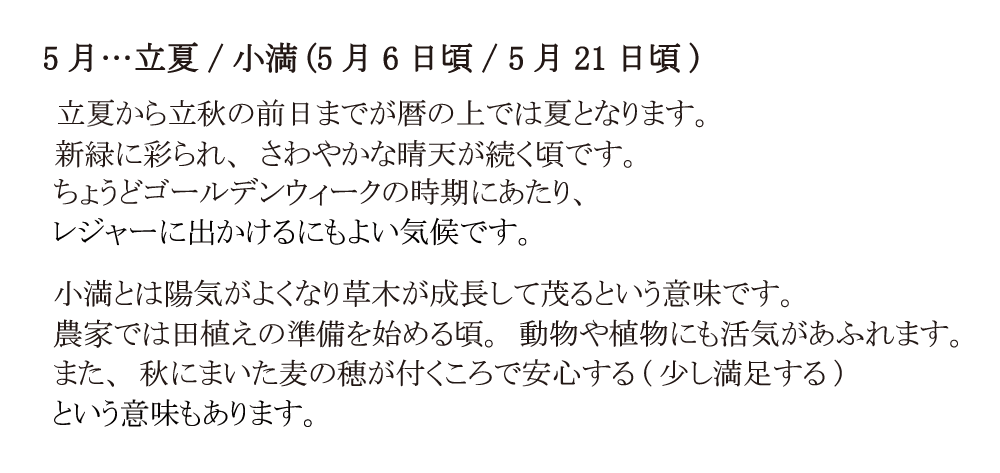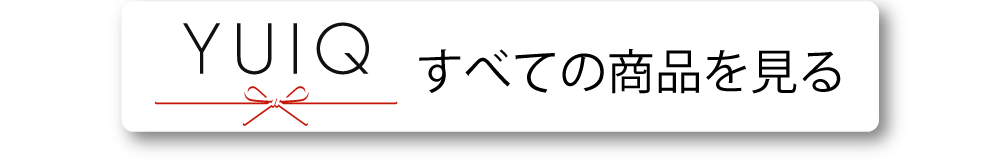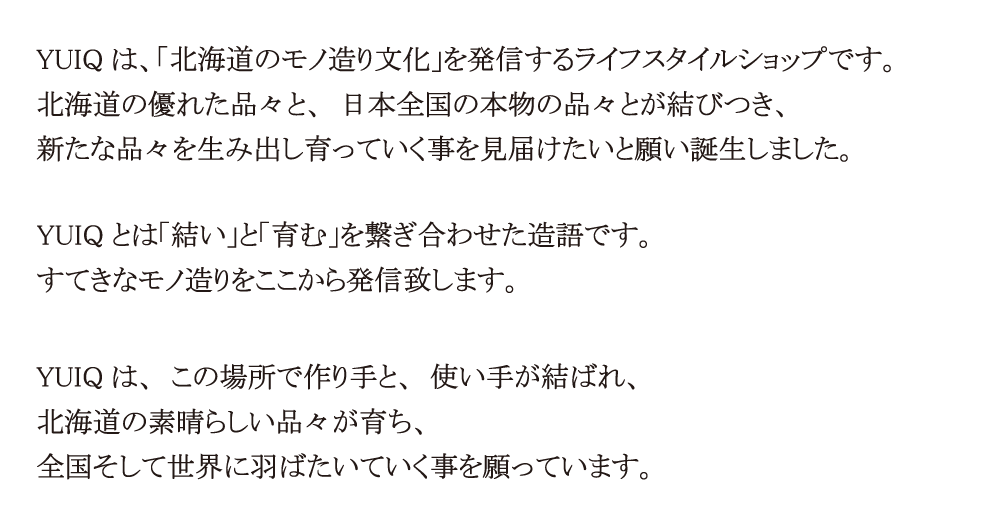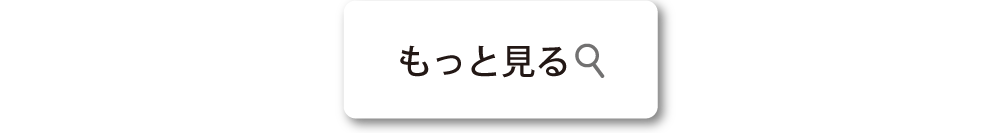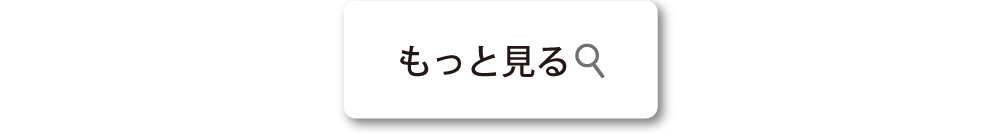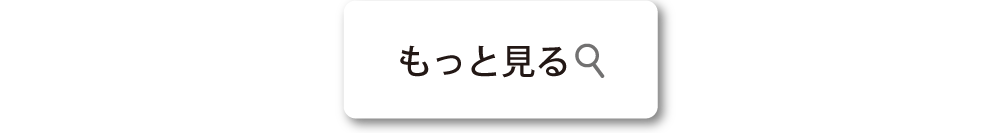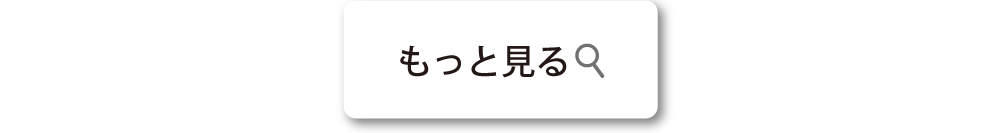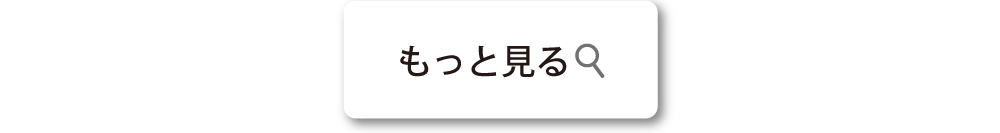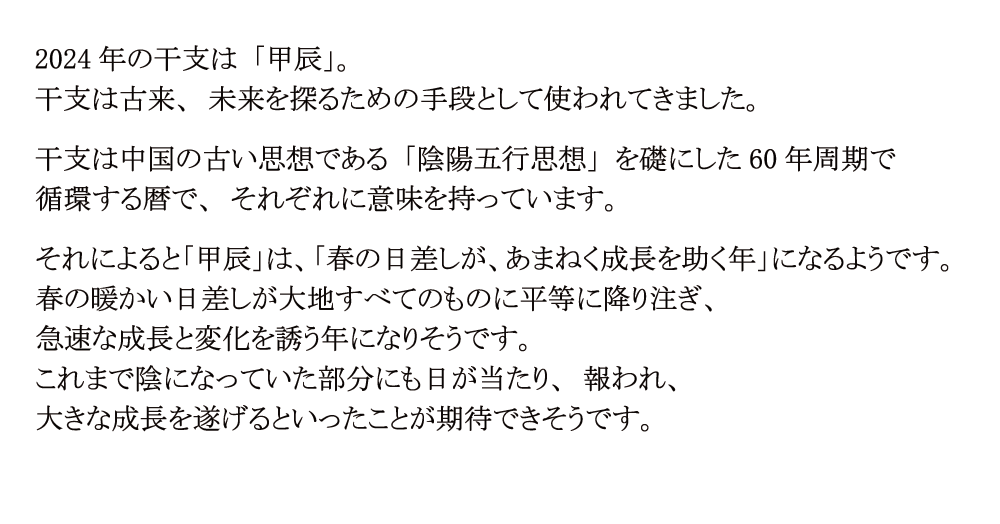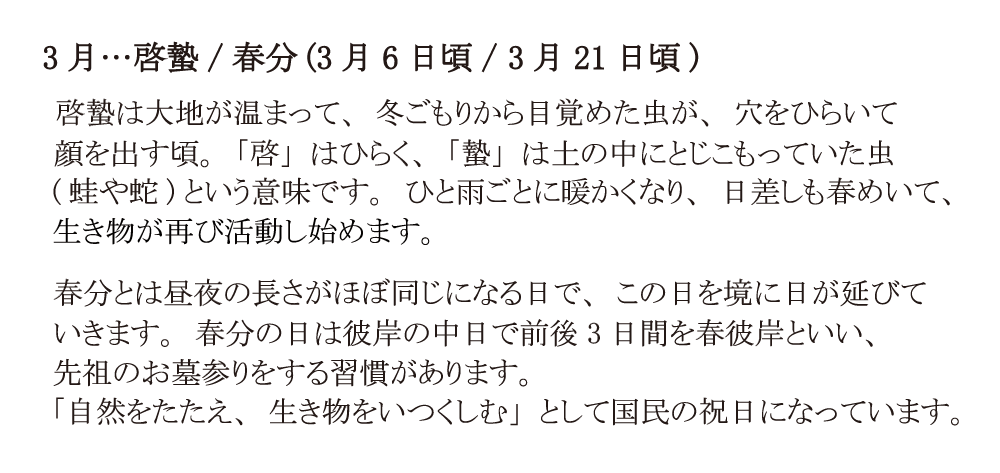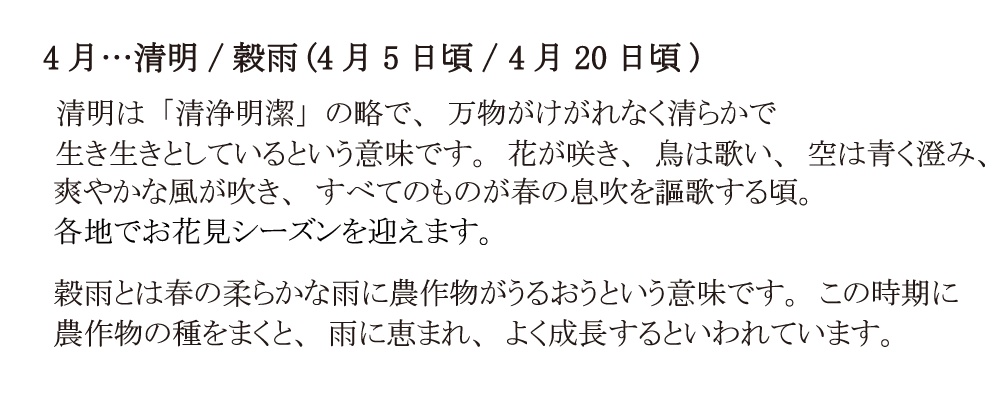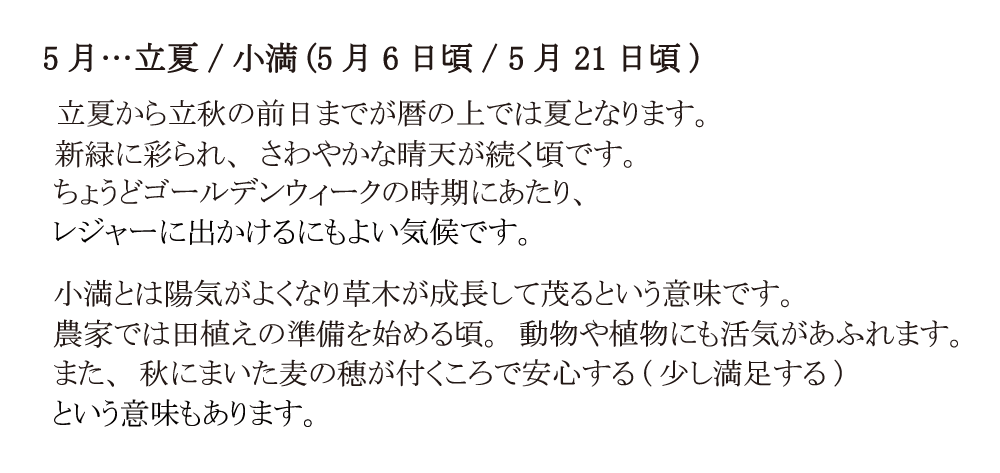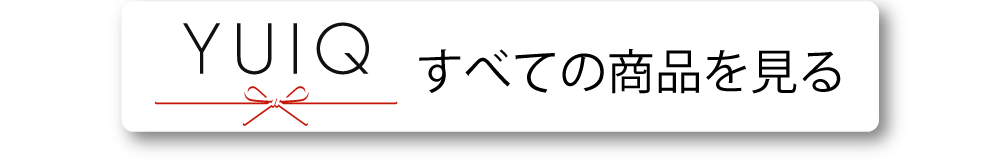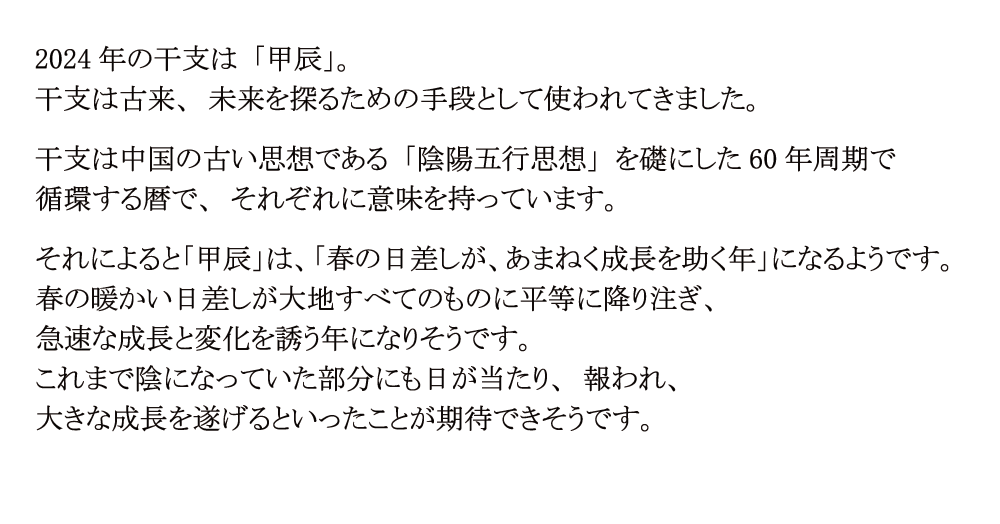 2024年の干支は「甲辰」。干支は古来、未来を探るための手段として使われてきました。干支は中国の古い思想である「陰陽五行思想」を礎にした60年周期で循環する暦で、それぞれに意味を持っています。それによると、「甲辰」は「春の日差しが、あまねく成長を助く年」になるようです。春のあたたかい日差しが大地すべてのものに平等に降り注ぎ、急速な成長と変化を誘う年になりそうです。これまで陰になっていた部分にも日が当たり、報われ、大きな成長を遂げるといったことが期待できそうです。
2024年の干支は「甲辰」。干支は古来、未来を探るための手段として使われてきました。干支は中国の古い思想である「陰陽五行思想」を礎にした60年周期で循環する暦で、それぞれに意味を持っています。それによると、「甲辰」は「春の日差しが、あまねく成長を助く年」になるようです。春のあたたかい日差しが大地すべてのものに平等に降り注ぎ、急速な成長と変化を誘う年になりそうです。これまで陰になっていた部分にも日が当たり、報われ、大きな成長を遂げるといったことが期待できそうです。
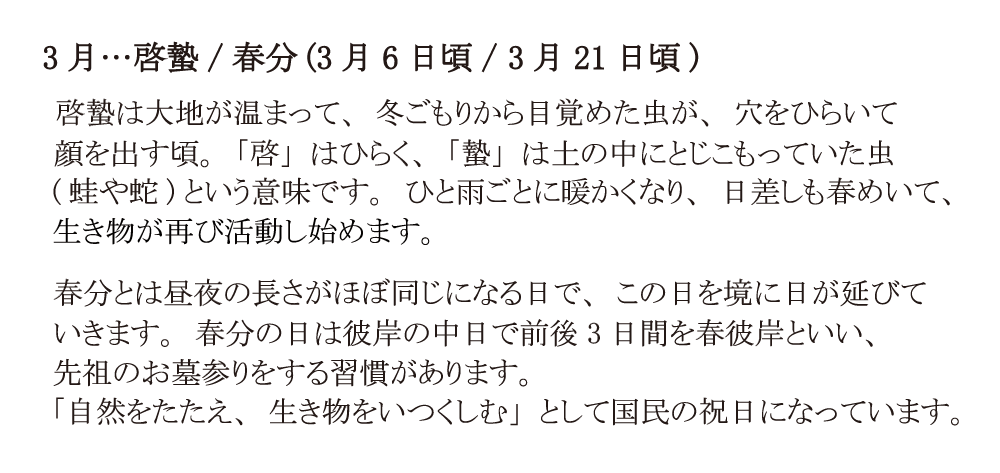
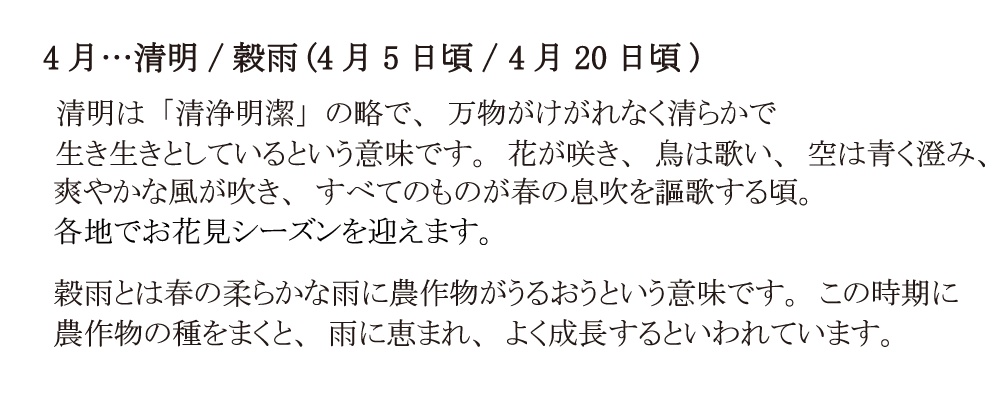
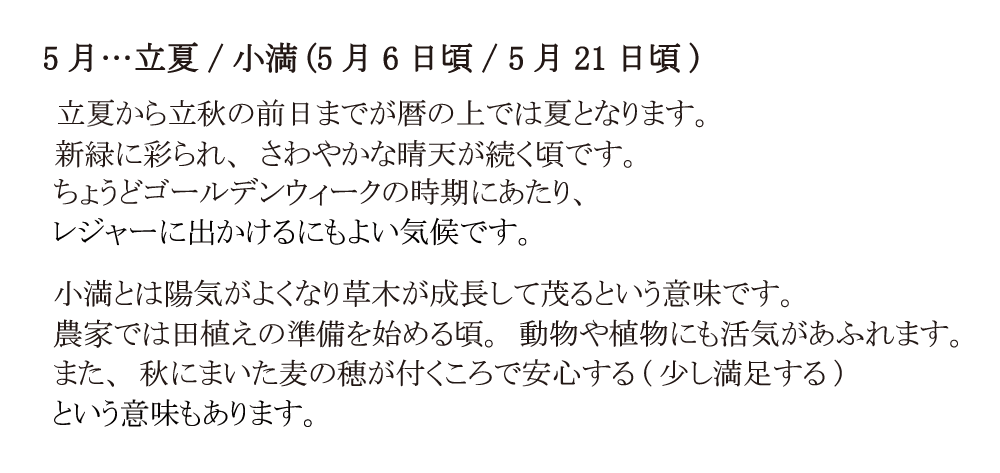
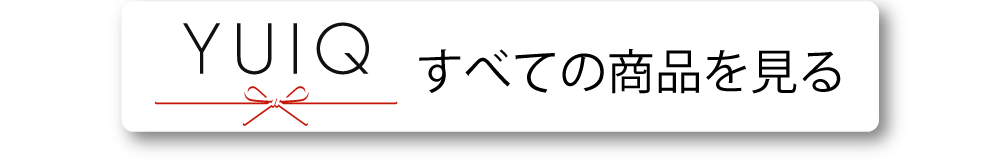 https://store.sweet-deco.jp/products/list?category_id=259
https://store.sweet-deco.jp/products/list?category_id=259
ページトップへ